1章. 聖書の基本
注) 聖書の基本など十分に分かってる、それより早く聖書の核心とやらに進みたい、という方は「2章. 聖書の核心」へとお進み下さい。
ここから本編
まずは聖書の基本から確認しておきましょう。残念ながら、ここに書かれていることの多くは長老や巡回監督たちもよく分かっていません。

今でこそ聖書はヘブライ語聖書(旧約)とギリシャ語聖書(新約)の2部構成となっていますが、聖書はもともとは3部構成でした。
しかも、ギリシャ語聖書を除いたヘブライ語聖書だけの3部構成だったのです。
- トーラー(モーセ五書)
- ネビイーム(預言者たち)
- ケトゥビーム(諸書)
ご存知でしたか?
聖書とは3部構成
実際に、イエス・キリストの発言を確認してみましょう。
西暦30年頃のこと、キリストは当時のユダヤ教の権力者たちに対して次のように言い放ったことがありました。
イエスは(サドカイ人たちに)答えて言われた、「あなた方は間違っています。聖書も神の力も知らないからです」
マタイ 22:29
実は、ここでキリストが言及している「聖書」にギリシャ語聖書は含まれていません。
なぜなら、キリストの時代にギリシャ語聖書は存在していなかったからです。まだ書き始められてすらいませんでした。
ギリシャ語聖書で一番最初に書き始められたのは『マタイによる書』で、執筆の時期はだいたいキリストの死後10年頃です。
では、キリストにとっての「聖書」とは一体なんだったのでしょうか。
それはヘブライ語聖書です。キリストにとって聖書と言えばヘブライ語聖書、つまり旧約聖書のことでした。
このようなわけで、キリストの頭の中では聖書とはヘブライ語聖書だけを指しており、それにギリシャ語聖書は含まれていません。
さらに重要な基本、それはキリストは正真正銘のユダヤ教徒だったという点です。
キリストは別に自分の宗教を新しく始めたかった訳ではありません。ですから、亡くなる時も敬虔なユダヤ教徒としてお亡くなりになりました。
そして、聖書という文書も本来キリスト教の聖典ではありません。聖書はもともとユダヤ教の聖典です。
そして古代から、キリストが誕生する前の紀元前から、ユダヤ教徒たちは聖書を3部構成としていました。
これは見過ごされがちな事実ですが、とても大切な聖書の基本でしょう。
ちなみにその3部とは、トーラー(Torah - モーセ五書)、ネビイーム(Nevim - 預言者たち)、ケトゥビーム(Ketubim - 諸書)です。
現在でもユダヤ教徒たちは聖書のことをタナハ(TaNaKh - 各書の頭文字)と呼んでいます。
そして、それぞれに収録されている書名と並び順は基本的には以下のようになっています。
この並び順こそが紀元前から伝わる聖書の伝統的な並び順です。
- トーラー(モーセ五書)
創世記・出エジプト記・レビ記・民数記・申命記 - ネビイーム(預言者たち)
ヨシュア記・裁き人・サムエル記・列王記・イザヤ・エレミヤ・エゼキエル・ホセア・ヨエル・アモス・オバデヤ・ヨナ・ミカ・ナホム・ハバクク・ゼパニヤ・ハガイ・ゼカリヤ・マラキ - ケトゥビーム(諸書)
詩編・箴言・ヨブ記・ソロモンの歌・ルツ記・哀歌・エステル記・ダニエル書・エズラ・ネヘミヤ・歴代誌
補足的な情報については Wikipedia の「ヘブライ語聖書」を参照して下さい。
さて、エホバの証人が本当にイエスに習いたいと思っているのなら、自分たちの認識をイエスの認識に合わせることから始めるべきではないでしょうか。
イエスにとって「聖書」と言えば、それはギリシャ語聖書を含んでいないタナハであり、そのタナハとは3部構成の聖典でした。
キリストは幼少の頃から敬虔なユダヤ教徒でしたから、先祖代々伝わる聖書の伝統的な区分を使うのはとても自然なことだったでしょう。
自分の家族もシナゴーグのラビたちも、聖書のその区分を使っていたでしょうから。
ほんの一例ですが、キリストが実際にその区分を使っている様子がこちらです。
第二もそれと同様であって、こうです。「あなたは隣人を自分自身のように愛さねばならない」。律法全体はこの二つのおきてにかかっており、預言者たちもまたそうです。
マタイ 22:37-40
こうして、義なるアベルの血から(創世記の記述)、あなた方が聖なる所と祭壇の間で殺害した、バラキヤの血に至るまで(歴代誌の記述)、地上で流された義の血すべてがあなた方に臨むのです(イエスが使っていた聖書は「創世記」から始まり「歴代誌」で終わっていた)。
マタイ 23:35
それから(イエスは)彼らにこう言われた。「まだあなた方と共にいた時に、わたしが話した言葉はこうでした。つまり、モーセの律法の中、そして預言者たちと詩編の中にわたしについて書いてあることはみな必ず成就するということです」
ルカ 24:44
ちなみにこの区分は、キリストだけに限らず、ギリシャ語聖書全体にわたりヤコブやパウロなど当時の弟子たちによっても多用されています。
それはあまりにも多用されているので意識して読みさえすれば、すぐにたくさん見つけることができるでしょう。
キリストに限らず、ヤコブやパウロといった初期クリスチャンたちもクリスチャンである以前にユダヤ教徒でしたから、自分たちの伝統的な区分を使うのはやはり当然と言えます。
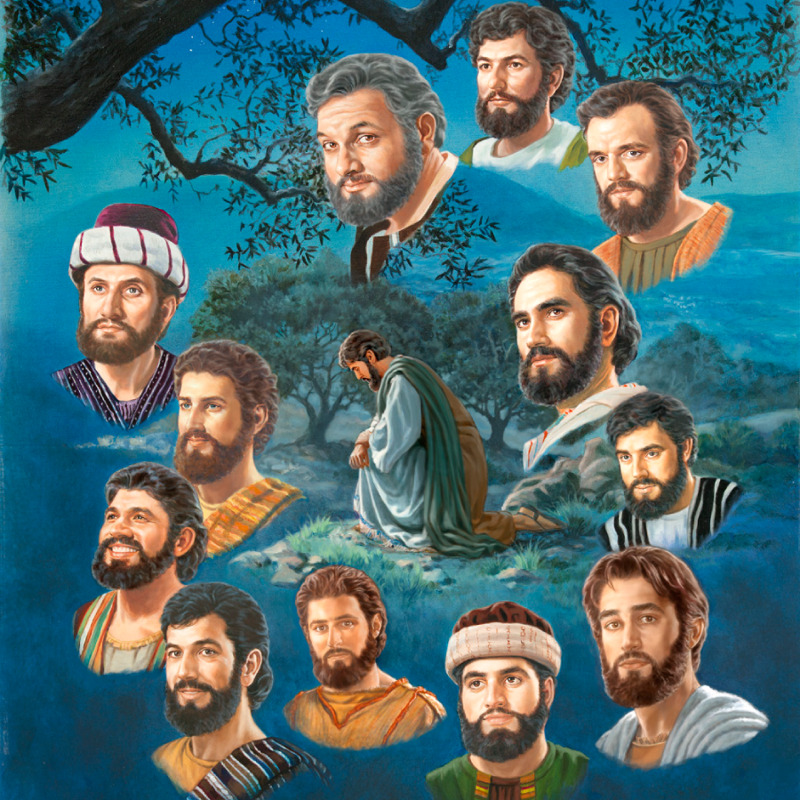
エホバの証人たちが本当にキリストや1世紀の弟子たちに習いたいと考えているなら、まずは彼らがそうしていたように聖書を3部構成として捉え直すのが良いでしょう。
ギリシャ語聖書の起源
さて、ここまでヘブライ語聖書の構成を見てきたわけですが、それではギリシャ語聖書は一体どこからやってきたのでしょうか?
このことに触れてから本章を終わりにしようと思います。
簡単に言ってしまえば、
西暦33年のキリスト殺害事件のあと、いわゆるクリスチャン(キリスト信者)たちが旧約を重んじるユダヤ教徒やローマ帝国の役人たちから激しい虐待を受けるようになりました。
このような激しい迫害を耐え忍ぶために、クリスチャンたちのコミュニティ間では当時たくさんの手紙や指示書がやり取りされるようになった訳です。
特に、キリストの直弟子であるペテロやヨハネ、パウロといった主要なクリスチャンが執筆した手紙は沢山のコピーが作られ、方々に散らばっていたクリスチャンのコミュニティ間で共有されました。

多くの手紙や巻き物が見える
このような経緯を経て、1世紀のクリスチャンたちの間で共有された大量の手紙や指示書のうち信憑性や権威を保ったもの、
これら大量の手紙や指示書が後世のキリスト教会によって厳選され、まとめられて「ギリシャ語聖書」と呼ばれるに至ったわけです。
ギリシャ語聖書(新約聖書)にどの手紙を収録するか、そしてどの手紙を収録しないかは、西暦397年8月28日のカルタゴ教会会議で決定されたとされています。
つまりギリシャ語聖書とはあくまで当時の手紙の厳選集であり、本質的には聖書ではありません。
過大評価も過小評価もしないこと、ありのままの姿を受け入れること、これが聖典研究のスタート地点です。
一方で、エホバの証人はギリシャ語聖書の捉え方において、かなりの過大評価をしています。
ギリシャ語聖書はキリストの言動録や黙示録を収録している点では確かに非常に特別な文書だと言えますが、そもそもヘブライ語聖書とは文書の性質が違います。
ゆえに、正真正銘の『聖書』つまり『旧約聖書 / タナハ』とはしっかり区別して学ぶべきでしょう。
エホバの証人たちは基本を知らない
今回取り上げた内容はその全てにおいて、聖書の基本中の基本だと言えます。
- 聖書はもともとユダヤ教の聖典
- 聖書はもともと3部構成(T-N-K)
- イエスや弟子たちもこの区分を利用した
- イエスや弟子たちはもともとユダヤ教徒
- 「聖書」とは基本的にタナハのこと
- 「新約聖書」とは当時の手紙の厳選集
エホバの証人たちはこれぐらいの基本は分かっている、と言いたいところですが、残念なことにエホバの証人たちは全く分かっていません。
キリストが言及している『預言者たち』に至っては聖書第2部タイトルではなく、文字通り「預言者の人たち」だと勘違いしています。
聖書がもともとユダヤ教の聖典だったこと、そしてキリスト本人を始め、ヤコブやパウロといった弟子たちがもともとユダヤ教徒だったこと、こういった認識もエホバの証人にはありません。
このように、エホバの証人たちは聖書の基本、聖書の大前提に非常に疎いわけです。
野球の基本ルールを知らない自称プロ野球選手のごとく。
これは会衆の兄弟姉妹たちは当然ながら、統治体たちにも共通して見られる彼らの特徴です。
なぜでしょうか?
理由はとても単純です。
エホバの証人たちは聖書の基本を教わる機会がないからです。これはどの会衆の兄弟姉妹たちも、ニューヨーク本部にいる統治体たちも同じです。
エホバの証人たちは聖書の情報に関しては完全に「ものみの塔聖書冊子協会」に依存しています。
統治体たちも基本的には、過去の歴代の統治体が生み出した聖書の見解を前提とします。
つまり組織トップから末端信者まで、エホバの証人にとっては組織こそが聖書に関するたった1つの情報源なのです。
ゆえに組織が教えてくれる事は知ってますし、組織が教えてくれないことは知りません。
聖書とはヘブライ語聖書であること、それは3部構成であること、キリストや弟子たちはユダヤ教徒であること、こういった基本に一生かかっても気付くことができないのです。
組織が教えてくれない、ただそれだけの理由で。
このような訳で、彼らは聖書を頻繁に学びながらも聖書の基本を学び損ねてしまいます。
こうして、聖書のメインテーマから外れてしまうエホバの証人たちが大量発生するわけです。
しかしこの点はパウロが警告してました。
(彼らは)常に学びながら、決して真理の正確な知識に達することができないのです。
テモテ二 3:7
では、無数のエホバの証人たちが生涯かかっても到達できない聖書の核心へと進みましょう。

